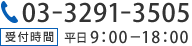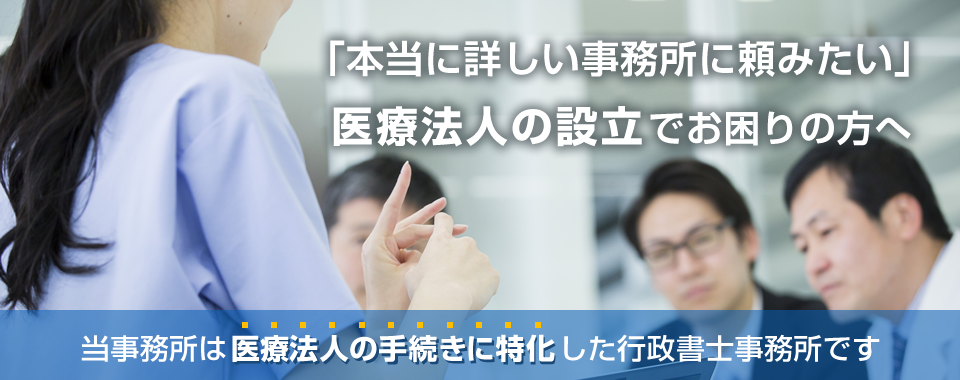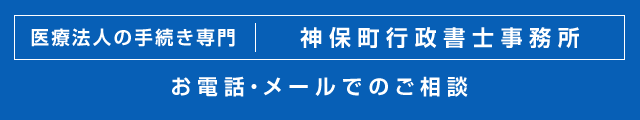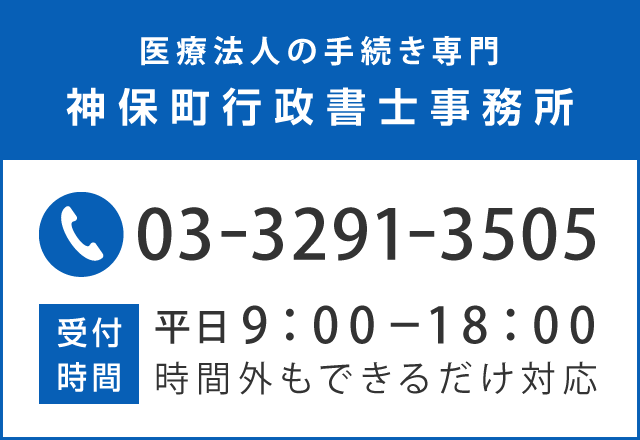分院開設するため個人診療所を開設して医療法人に取り込む方法
法人が分院を開設する場合定款変更に時間がかかるため、個人診療所を開設しておいてその後個人診療所を医療法人に取り込むこと方法がたびたびなされます。都道府県の定款変更に時間がかかり分院が開設できない期間が長期にわたると、特に借入により分院開設する場合、分院の収入がないまま借入金を返済しなければならず、死活問題になりかねないからです。
その場合、形式上①法人の勤務医(医療法第10条1項)が開設者=管理者となり(医療法第12条第1項)個人診療所開設し②勤務医が事業譲渡により診療所を医療法人に売却(実態は理事長が医療法人に売却)③都道府県に対する定款変更認可申請④法務局に登記⑤保健所に開設許可、開設届、エックス線装置設置届⑥厚生局に保健医療機関指定届という流れになります。
かように形式上勤務医が個人診療所を開設して法人への事業譲渡でありますが、実態が定款変更に先立つ分院開設であるため困難な問題が生じます。
①個人診療所の開設
通常の診療所の開設は開設者=管理者が資金を出し診療所を開設するのに対し、開設者=管理者は勤務医に過ぎないため診療所開設資金は理事長が出すことになります。しかし税務申告は開設者=管理者である勤務医名義でなされるから、理事長が出した資金で購入した内装設備、医療機器は勤務医所有としなければなりません。
医療法人は自分の診療所を運営する行為しかできない(医療法第39条)から、個人診療所の開設のための資金を出すことはできず、理事長が出さざる負えません。この点、個人診療所の開設も将来分院となるので自分の診療所を運営する行為にならないか、都庁に尋ねたところ、理事長が資金を出すように言われました。これをみとめると分院に取り込むといって法人が資金を出し、取り込まず個人診療所のまま放置されることもありうるからでしょう。
②事業譲渡
通常の個人診療所の事業譲渡の場合は、診療所の開設者=管理者である医師が医療法人に売却して、その対価をえますが、この場合、資金を提供してるのは理事長なので勤務医である診療所の開設者=管理者が対価をえないことになります。内装設備、医療機器等の所有権は税務申告をしている勤務医にせざる負えないので、事業譲渡は診療所の開設者=管理者である勤務医が、医療法人に売却することになりますが、その対価は資金を提供した理事長に支払われる第三者のためにする契約になります(民法第537条第1項)。
この場合の定款変更についても、事業譲渡なので都道府県より、事業譲渡契約書の提出を求められることになります。事業譲渡の金額が譲渡時の内装設備、医療機器等の簿価をいわれます。簿価にされた方がいいです。
事業譲渡により、診療所の賃借人が勤務医から医療法人にかわるので、定款変更にあたっては、賃借人の交代による覚書等を賃貸人に押印してもらうことが必要になります。勤務医名義で診療所を賃借する段階で、法人に賃借人に交代することがわかっているので、賃貸の段階でそのことを賃貸人に伝えておくといいです。
⑥保険医療機関指定申請
法人の分院開設とことなり、個人診療所を開設して法人の分院に取り込む場合保険診療は遡及します。
法人の分院開設のばあい、遡及は認められません。例えば、7月1日に開設許可が下りて、保険指定申請期間の7月1日~10日の間厚生局に保険医療機関指定申請をした場合、保険診療が可能なのは指定を受ける8月1日からになり、それまでは自由診療しか行えないことになります。
これに対して、個人診療所を開設して法人の分院に取り込む場合、8月1日に保険医療機関指定が受けたとしても、開設許可が下りた7月1日に遡及して、7月1日から保険診療できることになります。
医療法人の新規診療所(分院)の開設についてご相談してみませんか
当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
医療法人の新規診療所(分院)の開設等のお悩みのご相談に伺います。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。
ご依頼までの流れ
お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。
↓
当職 出張の上、ご相談いたします。
↓
お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。
↓
当職 見積もりをお送りいたします。
↓
お客様 見積もりを見てご依頼をされるか判断します。